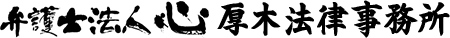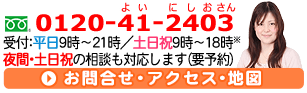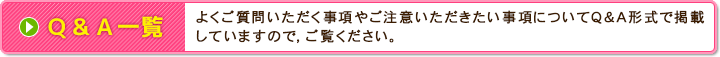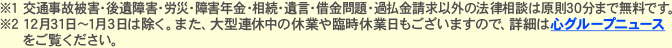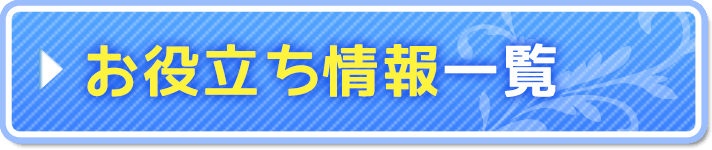認知症の人が書いた遺言書は有効か|遺言能力と判断基準
遺言書は、高齢になってから周囲の親族のすすめによって作成されることが多いため、加齢や認知症により判断能力が低下した状態で作成されることも珍しくありません。
遺言書は、将来の相続争いを防ぐための有効な手段ですが、認知症の人が遺言書を作成した場合には、遺言書の有効性を巡って相続人同士で争いが生じることがあります。
認知症の人は、遺言書を作成することができるのでしょうか。また、作成できたとしてもそのような遺言書は有効なのでしょうか。
今回は、認知症の人が書いた遺言書の有効性について解説します。
1 認知症の人が遺言を書いても有効?
⑴ 認知症だからといって直ちに遺言は無効にならない
遺言書の有効性については、後述する「遺言能力」の有無によって判断されます。
認知症だからといって、遺言能力がないとはいえず、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
認知症の人であっても、遺言書の内容を理解して、遺言書によってもたらされる効果を認識することができているのであれば、有効な遺言書を作成することができます。
⑵ 公正証書遺言の作成でも必須の遺言能力
認知症の人が作成した公正証書遺言の場合に、自筆証書遺言の場合よりも無効になることは稀、というのはあながち間違いではありません。
なぜなら、公正証書遺言を作成する場合は、公証人が遺言者の意思や遺言能力を確認して、2人以上の証人立ち合いの下で作成されるため、自筆証書遺言の場合よりも無効になり難いことは確かです。
ただし、公正証書遺言の作成にあたっても、遺言者には遺言能力が必要であることに変わりありません。
もし、子供が認知症を患った親に遺言書を書かせようと公証役場に連れて行き、遺言能力の確認が不十分なまま公正証書遺言を作成した場合には、後から遺言能力が問題となる可能性は十分あります。
2 遺言能力とは
有効な遺言書を作成するためには、「遺言能力」が必要とされています。
遺言能力とは、どのような能力をいうのでしょうか。
以下では、有効な遺言書の作成に必要とされている遺言能力について説明します。
⑴ 遺言能力としての行為能力
民法では、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」との遺言の行為能力を定めた規定をおいています(民法961条)。
15歳未満の人は、有効に遺言書を作成する余地は一切なく、他方、15歳に達した人は、未成年者であったとしても、法定代理人の同意を得ることなく、単独で有効に遺言書を作成することができます。
そのため、15歳以上であるということが有効に遺言書を作成する条件の1つとなります。
⑵ 遺言能力としての意思能力
未成年者や成年被後見人の法律行為は、取り消すことができるとされています。
しかし、遺言に関しては、民法総則の制限行為能力に関する規定は適用されません(民法962条)。
また、民法では、後見開始の審判がなされ、成年被後見人となった場合でも、一定程度遺言能力を回復した状態にある場合には、医師2人以上の立ち合いを条件として遺言書を作成することを認めています(民法973条)。
このようなことから、遺言能力としての意思能力は、取引上の行為能力よりも低い程度の能力で足り、実務においては、遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その結果もたらされる法律効果を弁識するのに必要な判断能力があれば足りると解されています。
認知症の人が書いた遺言書の有効性については、主に、遺言能力としての意思能力を有していたかどうかによって判断されることになります。
3 認知症の方が書いた遺言の有効性の判断基準
認知症の人が書いた遺言の有効性の判断基準は、主に、次の3点の事情を総合的に考慮して判断されることになります。
- 遺言時における遺言者の心身の状況
- 遺言内容それ自体の複雑性
- 遺言内容の不合理性、不自然性
以下では、それぞれの判断基準について詳しくご説明します。
⑴ 遺言時における遺言者の心身の状況
遺言能力の判断においては、遺言作成時の遺言者の心身状態が重要な事情となります。
遺言者が認知症と診断されている場合には、遺言能力が無いと判断される可能性は高まりますが、それだけで直ちに遺言能力が否定されるわけではありません。
遺言能力の有無については、以下のような医学的観点と行動観察的観点から判断していく必要があります。
- 精神医学的疾患の存否
- 遺言者が罹患していた精神医学的疾患が発現する頻度(恒常的なものか、一時的なものか)
- 遺言者が罹患していた精神医学的疾患の症状の内容・程度
- 遺言時またはその前後の遺言者の言動及び精神状態
医学的な判断とは異なり、法的判断では、遺言能力は、遺言内容との関係で相対的に決定されるものです。
したがって、遺言能力の判断には、遺言当時の行動から、遺言者がどの程度複雑な内容の遺言を理解することができたのかを推知する必要があるのです。
⑵ 遺言内容の複雑性
遺言能力の判断にあたっては、遺言の内容や効果を遺言者が理解していたかどうかもポイントになります。
そのため、単純な内容の遺言書の作成には、それほど高度な判断能力は必要ありませんが、複雑な内容の遺言書の作成には、より高度な判断能力が必要となります。
たとえば、「すべての財産をAに相続させる」という遺言と「甲不動産についてはA、乙不動産についてはB、丙不動産についてはC」という遺言を比べると、前者の方が判断能力の程度が低くても足りるということは、ご理解いただけるでしょう。
⑶ 遺言内容の不合理性・不自然性
遺言の内容自体も遺言能力の有無を判断する要素となります。
生前の遺言者と相続人や受遺者との関係に照らして、遺言内容と遺言者の意図・動機とに乖離があると推定される場合には、不合理な遺言内容と判断される可能性があり、遺言能力を否定的に解する事情になり得ます。
また、遺言者が何度も遺言の内容を大きく変更している場合には、不自然な遺言内容と判断される可能性があり、これも遺言能力を否定的に解する事情となり得ます。
遺言内容の不合理性・不自然性は、生前の遺言者と相続人や受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯といった遺言当時の遺言者の周辺事情をもって立証することになります。
具体的には、遺言者の日記、メモ、遺言者の同居・生活状況、旧遺言の有無、旧遺言がある場合には当該遺言内容との比較によって立証していきます。
4 遺言の有効・無効で争っている場合の解決方法
すべての相続人が、遺言書が無効であることを認めているのであれば、相続人全員で遺産分割協議をすることで、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることができます。
しかし、遺言書の有効性を争う相続人がいる場合には、以下のような手段によって遺言書の有効性を確認しなければなりません。
⑴ 遺言無効確認調停
被相続人の遺言が無効であることについて、相続人全員が合意できない場合には、家庭裁判所に対して遺言無効確認調停を申し立てます。
遺言が無効かどうかについては、裁判所が法的に判断を下す前に、調停で当事者同士により話し合いをすることが好ましいという判断から、調停を申し立てることなく遺言無効確認訴訟を提起することはできません。
これを「調停前置主義」といいます。
遺言を無効とすることに合意ができた場合には、調停が成立しますが、一人でも無効を認めない相続人がいる場合には、調停は不成立となります。
⑵ 遺言無効確認訴訟
遺言無効確認調停が不成立となった場合には、次の段階として、遺言が無効であることを裁判所に確認してもらうために、地方裁判所に対して遺言無効確認訴訟を提起することができます。
認知症を理由として遺言無効確認訴訟を提起する場合には、原告において、前述の遺言能力の判断基準を踏まえて、遺言者に判断能力が無かったことを具体的に主張・立証していかなければなりません。
その際には、文書送付嘱託などの手続きを利用して、被相続人のカルテや診断書、要介護認定の資料などを取り寄せるということも有効な手段となります。
遺言無効確認訴訟では、最終的には当事者の主張立証を踏まえて裁判官が判決を言い渡します。
判決で遺言の無効が確認された場合には、当該遺言は、無効となり存在しないものとして扱われます。
そのため、判決が確定した後は、相続人同士であらためて遺産分割協議を行って被相続人の遺産の分割方法を決めなければなりません。
遺言無効確認訴訟では、あくまでも遺言が無効かどうかについて判断されるだけであり、具体的な遺産の分割方法まで決まるわけではない点には注意が必要です。
5 認知症と遺言の効力については弁護士にご相談ください
認知症の人が書いた遺言書であっても直ちにその効力が否定されるわけではありません。
しかし、遺言書の内容に不満がある相続人からは、認知症を理由として遺言の無効が主張されることがあります。
遺言の有効性が確定しなければ、具体的な遺産分割の手続きは進みません。
したがって、遺言書の有効性に疑問が生じる事案では、すべての相続手続きが完了するまでに相当長期間を要することになります。
そのため、遺言書を作成しようと考えている方は、相続人同士の争いを防止するためにも、早いうちから遺言書の作成に取り掛かることをおすすめします。
また、実際に争いが生じた場合にも弁護士にサポートを受けながら進めていくとよいでしょう。
遺言の有効性を巡って相続人間で争いが生じているのであれば、ぜひ一度弁護士法人心へご相談ください。
相続を得意とする弁護士が、ご相談をお待ちしております。
遺言について弁護士への相談をお考えの方 遺産分割にお悩みの方へ