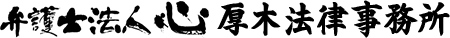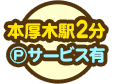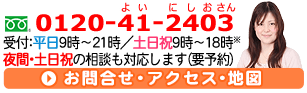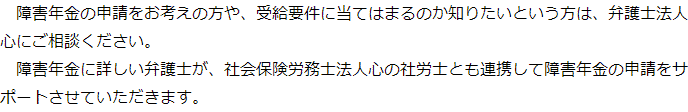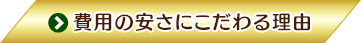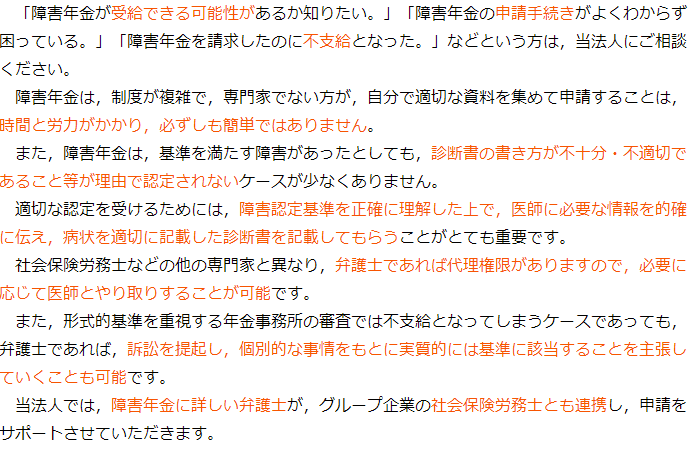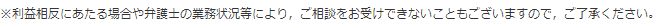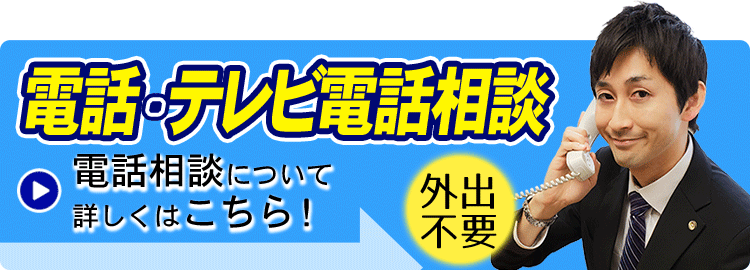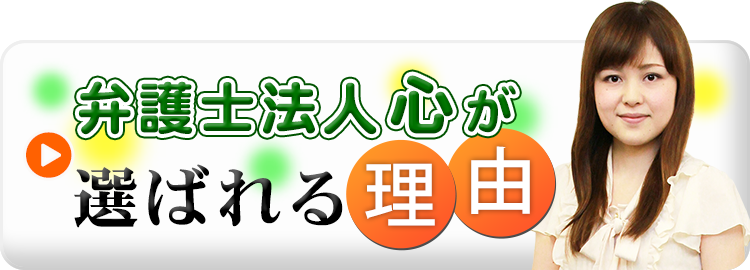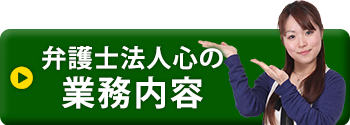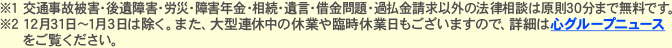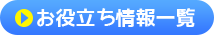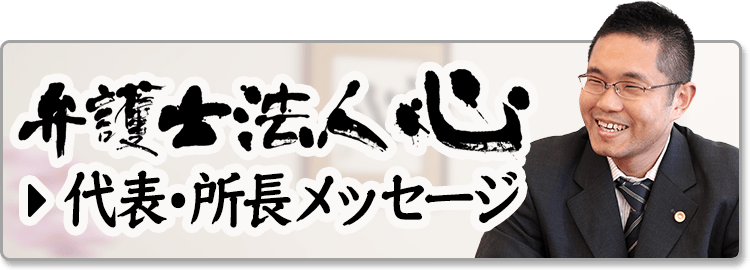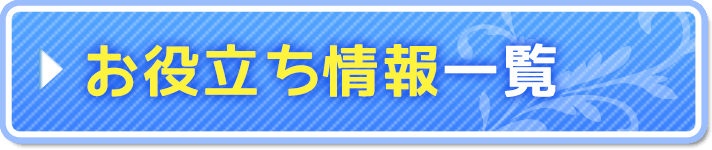障害年金
障害年金はいつからもらえるのか
1 障害年金の請求方法
障害年金の請求方法には、「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」の3種類があり、請求ごとに、どの時点から障害年金が受給できるのかが異なります。
以下、請求ごとに、いつから障害年金がもらえるようになるのかについて解説します。
2 認定日請求の場合

「認定日請求」とは、障害認定日における障害の程度が、障害年金を受給できる程度に達していた場合に行うことのできる請求方法です。
「認定日請求」が認められた場合は、障害認定日に障害年金の受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月分から、障害年金を受給することができます。
なお、「障害認定日」とは、①初診日から1年6か月経過した日、あるいは、②初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は「治った日(=その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)」のことをいいます。
3 遡及請求の場合
「遡及請求」とは、認定日請求のうち、障害認定日の時点において障害の程度が障害年金を受給できる程度に達していたものの、障害認定日の到来後すぐに障害年金の請求をしていなかったという場合に、障害認定日に遡って障害年金の請求をする方法のことをいいます。
「遡及請求」も認定日請求の一種ですので、障害認定日に障害年金の受給権が発生するのですが、障害年金には5年の消滅時効がありますので、際限なく認定日まで遡ることができるわけではなく、遡って請求ができるのは、請求日から過去5年分に限られます。
4 事後重症請求の場合
「事後重症請求」とは、障害認定日の時点では症状が軽かったため障害年金を受給できなかったものの、障害認定日以降に、障害の程度が障害年金を受給できる程度に達したという場合に、重症化した後の症状に基づき請求をする方法のことをいいます。
「事後重症請求」の場合は、障害認定日ではなく、請求日時点で受給権が発生し、請求日の属する月の翌月分から障害年金が支給されることになります。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 働きながらでも障害年金を受給できる場合があります!
障害年金は、病気や怪我によって日常生活や就労が制限されてしまっている場合に受け取ることのできる年金ですので、このような障害年金の性格からすると、働いている場合には障害年金を受給することはできないと思われている方も少なくありません。
もっとも、実際は、働きながらであったとしても、障害年金を受給することができる場合がありますので、以下でご紹介したいと思います。
2 就労の有無にかかわらず障害年金の受給対象となる扱いがされているケース

障害年金の制度においては、就労の有無にかかわらず、障害年金の受給対象とされているものがあります。
例えば、関節を人工関節に置換している、心臓ペースメーカーを入れている、人工透析を行っている、人工肛門を造設しているなどです。
これら場合は、仮にフルタイムで仕事をしていても障害年金を受け取ることができます。
また、視力障害や聴力障害など、数値が一定の水準に達していれば障害年金の対象となるように扱われているものもありますので、このような障害の場合も基準を充たしてさえいれば、働いているか否かにかかわらず、障害年金を受給することができます。
3 就労の有無が障害年金の受給に影響を及ぼすケース
精神や内科系の疾患の場合は、障害によって実際に日常生活や仕事にどのような影響が生じているのかを確認されますので、働いていることは障害年金の受給の可否に影響を及ぼします。
もっとも、これらの疾患の場合でも、働いていたら必ずしも障害年金が受給されないというわけではありません。
例えば、遅刻・早退・欠勤の数や職場からの勤務内容や勤務時間に対する特別な配慮の有無などを考慮した結果、障害年金が受給できる場合もあります。
そのため、働いているものの、精神や内科系の疾患で障害年金を受給したいという方は、就労の状況や職場から受けている特別な配慮の内容、就労後の心身の状況等を、正確に医師に伝えていただき、診断書に反映してもらうことが重要です。
障害年金を申請する際に注意すべき点
1 障害年金申請にあたっての注意点

障害年金を申請するにあたって、どのように進めればよいのか、気を付けるべき点等が分からないという方は多くいらっしゃると思います。
障害年金を申請するにあたって、どんなことに注意しておけばよいのかについて、いくつかご説明いたします。
2 受給要件を満たしていないとそもそも受給できない
65歳から受け取る年金(老齢年金)も、未納状態が続けば受給額は減少し、最終的に1円も受け取れなくなる可能性があります。
障害年金も年金制度の1つであり、原則として保険料の納付が前提とされています。
保険料納付の要件を満たしていないと、そもそも受給ができないとうことはご注意いただきたいと思います。
3 所定の書式を用いて申請を行う必要がある
障害年金を申請するには、いくつかの必要書類を用意する必要がありますし、書式も決まっています。
診断書の作成はお医者様に依頼することになりますが、どんな体裁でもよいというわけではなく、障害年金申請用の診断書に必要事項をご記入いただく必要があります。
4 他の制度と受給の調整が行われる場合がある
例えば、生活保護と障害年金とを二重に受給できるわけではなく、総受給額の調整が行われます。
生活保護単体で8万円受け取れるとして、障害年金の受給額が6万円と決定された場合、合計14万円ずつ受け取れるようになるのではなく、生活保護が2万円、障害年金6万円で、合計額が生活保護受給額の8万円と同額となるように調整される、といった具合です。
類似の調整として健康保険の傷病手当金や、労災等とも調整が図られるようになっています。
5 審査は基本的に書面のみで行われる
障害年金の申請をしたあと、担当者と面接をしたり、医師が派遣されて改めて検査を行ったりということはなく、基本的には申請した書類の内容で障害年金の受給が認められるか否かを判断されることになります。
特に、精神疾患や、四肢の麻痺等については、日常生活状況等の総合判断となり、数値的な基準(例えば両目の視力が0.03以下等)となっていません。
診断書等の作成をお医者様に依頼する際には、日常生活でのお困りごとなどをしっかりお伝えしておくよう注意しておくとよいかと思います。